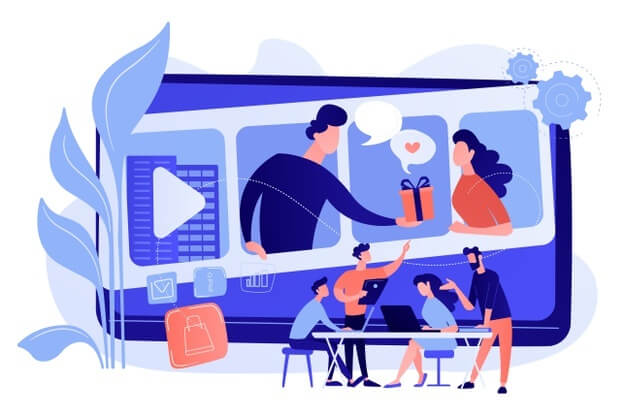「実際のところオンラインイベントってどうなの?」という気になるところを弊社代表の桑原とイベントプロデューサーの前田(通称:マエケン)に語ってもらう対談企画第2弾。
前回は、どんどん進化するオンライン配信の機能を駆使しながら、誰もがつながれるグローバルなオンラインイベントの作り方について詳しく話してくれましたが、今回も熱い思いが終始飛び交っておりました!
- ーー:
- 桑原さんは最近特に印象に残ったオンラインイベントはありますか?
- 前田:
- 僕は桑原さんが手掛けていたB社がすごく気になってたんですよ!
- 桑原:
- B社のことは僕もすごく話したかったんだよ。
この会社さんは、例年は新年会を兼ねた経営方針発表会を1月にやっていて、、今回でうちがお手伝いし始めてから、7回目の開催だったんだ。
いつもは3か月くらい前に連絡がきてキックオフしていたけど、今回は半年以上前に連絡がきたんだよ。やはりリアル開催が難しいということで、担当者さんも心配していたんだろうね。
- 前田:
- これまではずっとリアルで開催していて、B社の社長もみんなが集まらないと意味がないっていう考えでしたよね。
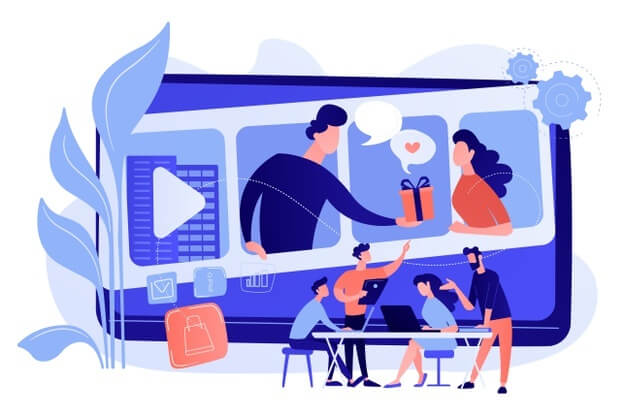
今後もっとも期待される「マルチベニュー型」
- 桑原:
- B社は全国に社員の方がいるんだけど、イベント会場として全国に6つの会場を設けて、それぞれの会場に少人数を集め、しっかりディスタンスをとりながら会場と会場をつないで進行するマルチベニュー型を提案したんだよ。
- 前田:
- マルチベニュー型って音声がずれるんじゃないかっていう心配がありましたけど、配信技術の進歩で遅延も改善されましたよね。
- 桑原:
- イベントは人と人とが集まってやらなきゃ意味がないって考えだったから、そのやり方でいこうと全国の下見までしてたんだよ。残念ながら今回は緊急事態宣言が発令されてマルチベニューではできなかったんだけど、B社もこんな方法があるんだって盛り上がってたんだよね。
- ーー:
- ハイブリッド型とマルチベニュー型との違いは何ですか?
- 前田:
- オンラインとリアルを組み合わせてひとつのイベントをやるっていうのがハイブリッド型イベントです。マルチベニュー型は、ひとつのイベントを一か所で行うのではなく、各地方に会場を設けて、その会場と会場を遠隔でつないで進行するやり方です。形上は、リアルイベントですね。
- 桑原:
- マルチベニュー型は各地域の各会場に集まって、会場同士を配信でつないでいくもの。例えば、東京がメイン会場として進行していても、受賞者が大阪にいれば大阪会場がメイン会場になるっていう多地点展開だね。これができればイベント業界ももっと盛り上がっていくと思う。
- 前田:
- コロナが緩やかになってきたら、全国から東京に集めるイベント形式ではなく、各地方の会場に集まって、自分たちの会場から受賞者が選ばれる興奮を味わえるような、オンラインだけどリアルを感じられるようなイベントがメインになってくると思ってます。
イベント成功の鍵は「綿密な準備」と「スムーズな進行」
- ーー:
- 惜しくもマルチベニュー型でのイベント開催はできなかったB社ですが、今回はどんな方法をとったんですか?
- 桑原:
- 今回は完全にオンラインで、それぞれのパソコン環境から900人の方が参加したんだよ。B社はもともと、社長の話の後に受賞者を発表するだけの表彰式をして、懇親会もなしっていう進行で考えてたんだけど、ZoomとGoogle Meetの2つのプラットフォームを併用するという我々の提案を採用していただけて。
- 前田:
- 2つのプラットフォームを併用することで、よりスムーズに進行できますよね。
- 桑原:
- 基本的にはZoomで進行して、表彰における各賞のノミネート者は、あらかじめ別に用意したMeetの部屋に集められていて、受賞者が発表された瞬間から、受賞理由が読み上げられる間に、受賞者は裏でZoomに移動してピン留め。そして受賞スピーチの瞬間には受賞者が全画面に映し出されるようにしたんだよ。
- 前田:
- そういうやり方って複雑でややこしいんですけど、上手く段取りを組むことで実現できるんですよね。
- 桑原:
- 受賞者をこれまで支えてきた上司や仲間たちも同じ場所にピン留めして、受賞者を中心にみんながひとつに収まる画をつくって話してもらう演出を加えたことで、組織としての一体感を強く感じられたと思う。
- 前田:
- 綿密な準備とスムーズな進行があったからこそ、参加者が、ストレスなく楽しく視聴することができて、狙いだった、帰属意識や一体感を生むことができたのでしょうね。

オンラインだからこそ伝わる思い
- 桑原:
- リアルでの開催しか考えられないと言っていた社長も、休憩時間に「このやり方ええなぁ!」「わしもやってて興奮するわ!」と声をかけてくれて嬉しかったなあ。終了後のフィードバックでも、社員の満足度が98%まで上がったんだよ。
- ーー:
- それはすごいですね。今までのリアルイベントとの違いは何だったのでしょうか?
- 桑原:
- アンケートを読むと、今までは社長が発信している話に、参加者が聞いていてうまく自分のチャンネルを合わせられず、みなさん実は話を聞いてるふりをしていたと。でも今回はオンラインだったからこそ、「社長の言葉の奥にある『本音』を絶対掴んでやろう」という思いで聞くことができたって声もあったね。
- 前田:
- 社長が一生懸命に緊張しながら話す、普段は絶対に見られない姿を見られるのもオンラインのよさですね。
- 桑原:
- B社のような全国規模の会社がオンラインでイベントを開催して、受賞者をしっかり激励して、社長の思いもちゃんと伝わって、その上コストがリアルイベント開催時の半分以下だったということで非常に満足していただけたんだよね。実はそのイベントが非常によいものだったので、その日以降、自分自身B社ロスに陥ってしまったわ(笑)
ハイブリッド型イベントの始まり
- ーー:
- おふたりの印象に残っているイベントのお話をもっと聞かせていただけますか?
- 前田:
- 去年の夏に開催した、S社のハイブリッド型表彰式ですね。
- 桑原:
- マックスプロデュースとしても初めての試みだったし、ハイブリッド型イベントのスタンダードな実績となって、各クライアント様にもご提案できたよね。
- 前田:
- S社はリアルからオンラインに切り替えるのも早かったのですが、密を避けることを第一に考えながらイベントを企画しました。
- 桑原:
- 緊急事態宣言が解除された後で、社員さんたちは会社に出社してたから、会社のカフェラウンジに特設ステージを設けて、そこから配信をする形にしたんだよね。
- 前田:
- 企画の内容は、各賞のノミネート者が各フロアの執務室で仕事をしている中で、ステージでは受賞者が発表されます。すると、その受賞者のところにS社の事務局の方がライブカメラをもって突撃するというもの。驚きながらも喜びの表情を浮かべてステージに立つ受賞者を拍手で称えてあげるサプライズ演出でした。
- 桑原:
- 最大限に密を避ける形のけっこうおもしろい試みだったね。その後もS社はそのやり方を採用してるみたいで、会社の中でもかなり大きな実績だったんじゃないかな。その後、C社やF社でもそのやり方が採用されて。
- 前田:
- 最初は僕も勉強しながら制作を進めていったんですけど、ハウリングしないかものすごく心配だったんです。そこで、自分の声だけをミュートにするマイナスワンという技術を知りました。
- 桑原:
- ハウリングはもちろんのこと、自分の話した声がスピーカーから2秒後に返ってきたりするエコーがかかっちゃうとしゃべれなくなるから、音の回りはオンラインイベントにおいて最大の懸念ポイントだよね。
- 前田:
- まさにマイナスワンという技術は、オンラインイベントにおける希望の光でしたね。この技術がなかったらS社のイベントもできなかったと思います。
オンラインイベントは「攻め」の一手
- 桑原:
- その会社の理想のゴールにたどり着くための手段を私たちが提案しながら、一緒にイベントを作りあげることができたとき、業者とクライアントっていう関係だけじゃなくて、人と人との絆みたいなものが必ず生まれるよね。
- 前田:
- 先方と我々の思いがひとつになるから、一緒に喜び合えるんですよね。そういった意味では、リアルよりもむしろオンラインイベントってとても効果的な手法のひとつだと思います。妥協策じゃないんです。
- 桑原:
- 「妥協」じゃなくて、「成功」の手段なんだよね。コロナ禍で大事なのは攻めるか攻めないか。指をくわえて何もしないでいるか、今だからこそできることを探すという「攻め」の一手を打つかのどっちかだと思う。
- 前田:
- オンラインイベントを選ぶことは絶対に守りではないと思います。社員のことを思うがゆえの、「攻め」の一手なんです。
オンラインイベントは、受賞者の表情や涙、社長の熱い思いが画面上でもしっかりと伝わるため、より心に響くものになるんですね。リアルイベントができない今だからこそ、攻めのオンラインイベントが会社に変化をもたらすのだと思います。
今後ますます進化していくオンラインイベントですが、各会場をつないで一体感や没入感を味わえるマルチベニュー型でのイベント開催が待ち遠しいですね。
まだまだ熱い対談は続きますので、次回の投稿もお楽しみに~!